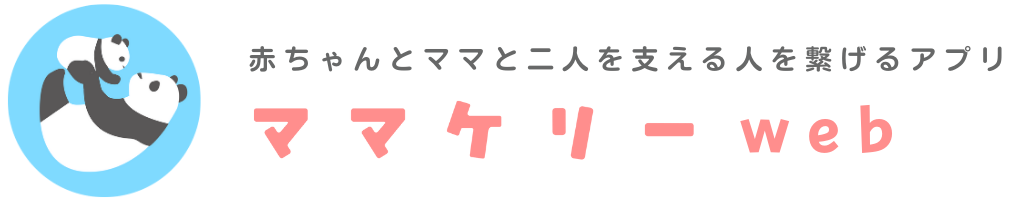毎朝子どもを起こすのは、親の大変な仕事です。
ただでさえ忙しい朝の時間に、
なかなか思うように子どもが起きないと
困ってしまいますよね。
しかし、寝起きが悪いのには原因があり、
生活を工夫することで解決できるかもしれません。
今回は、寝起きが悪い原因や、
スッキリ目覚めるためのコツなどをご紹介します。
子どもの寝起きが悪いのはなぜ?
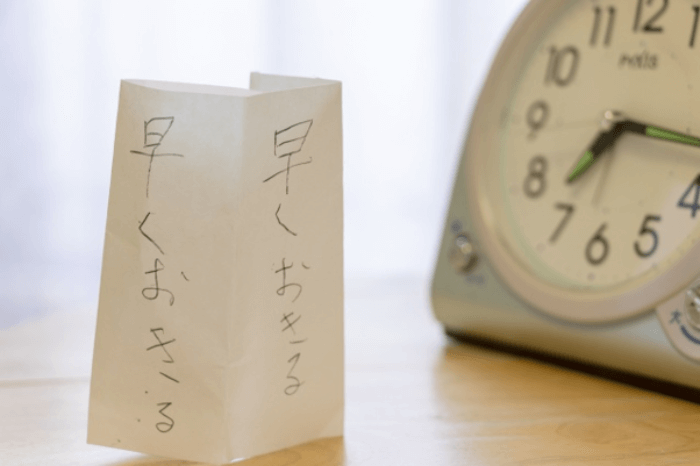
子どもの寝起きが悪いのは、睡眠時間の短さだけでなく、
睡眠周期や睡眠環境、心理的な要因なども
関係していることがあります。
メラトニンという睡眠ホルモンは、
子どものからだでは分泌が遅いだけでなく、
分解も遅い傾向にあります。
そのため、それらを助長する生活習慣は
睡眠不足に拍車をかけてしまいます。
睡眠時間が足りていない
保育園から小学校、さらに中学校へと成長する過程で、
子どもの体格は変わり、
勉強時間や生活習慣も変化していきます。
そのため、年齢に応じて必要な睡眠時間の確保が大切です。
米国睡眠学会によると、
3~5歳の子どもは10~13時間、
6~12歳では9~12時間の睡眠時間が必要
だといわれています。
たとえば小学生で、毎朝6時半に起きる場合は、
夜9時頃には就寝するのが理想的でしょう。
眠りが深い
人間の眠りは、浅い眠り(レム睡眠)と
深い眠り(ノンレム睡眠)の2つを
交互に繰り返すことで構成されています。
しかし、年齢の小さい子どもほど、
深い眠りが多いといわれています。
そのため、発達途中の子どもは
深い眠りについていることが多く、
それも寝起きの悪さの原因です。
睡眠環境が整っていない
部屋の照明や寝具、臭いや音など、
安らげない環境ではぐっすり眠れません。
心地よく、リラックスできる寝室を作ることも大切です。
学校や保育園に行きたくない
ストレスを言語などでうまく発散できない子どもの場合、
SOSのサインは食欲や睡眠、行動、感情などに
あらわれることがあります。
「いつもと違う」ことに気がついたら、
学校や保育園に行きたくないストレッサーが
あるのかもしれません。
いつもと違う不調が続いているときは、
担任の先生に日中の様子などを聞いてみると
原因が解決されることもあるでしょう。
スッキリ起きるためにパパ・ママができること5選

寝起きの悪い子どもに対して、朝スッキリ起きれるように
パパ・ママが工夫できることをご紹介します。
どれも簡単ですが大切なことですので、
是非やってみてください。
日の光が当たるようにする
朝起きたら、まずはカーテンを開けて
日の光を浴びましょう。
そうすることで、睡眠ホルモンであるメラトニンが減少し、
体内時計がリセットされます。
徐々に生活音が聞こえるようにする
朝、いきなり大声で起こすのではなく、
お湯が沸く音や、朝食の香り、テレビの音など、
一日がはじまる合図でもある生活音を
聞こえるようにしてみましょう。
洗濯機や掃除機をかけてみるのもいいかもしれません。
寝室の温度や寝具が適切か検討する
睡眠の質を上げるには、睡眠環境を整えることも大切です。
一般的に、寝室の温度は20℃前後、
湿度は約50%くらいが理想です。
また、マットレスの固さや寝具の肌ざわり、
枕の高さ、部屋の照明なども適切か見直してみましょう。
就寝前にスマホやゲームにふれないようにする
スマホやゲームの画面から発せられるブルーライトは、
夜に浴びるとメラトニンの分泌が抑制されて、
体内時計を遅らせてしまいます。
できるだけ、スマホやゲームの画面を見るのは
就寝の2時間前までにしましょう。
子どもの話を聞き、楽しい会話をする
子どもが起きてきたら、今日の予定や、
楽しい行事など気分が明るくなる会話をしてみましょう。
子どもから何か話してきたときはよく聞き、
一緒に楽しい気分になることで、
交感神経が優位になり目覚めがよくなります。
怠けているわけじゃない! 病気の可能性も?

生活スタイルや対処法を試してみても、
寝起きが改善されない場合は、
病気が隠れている可能性もあります。
- 睡眠時無呼吸症候群
- 不眠症
- 概日リズム睡眠障害
- むずむず脚症候群
- 起立性調節障害
など、自分ではどうにもできない病気も考えられます。
夜に眠れない、日中の眠気が強すぎるなどの症状が
1か月以上続く場合は、専門科の受診も検討してください。
生活リズムを整えるには漢方もおすすめ

「子どもが朝なかなか起きてくれない」と悩む方は、
漢方薬を活用するのもおすすめです。
寝起きが悪くなる原因としては、
- ストレスなどの心理的原因
- 過労などの心身的原因
- 血流不足
などが考えられます。
その改善には鎮静作用を含む漢方薬に加え、
- 自律神経の乱れを整え、ストレスが原因の疲労や睡眠の質をよくする
- 栄養を全身に届けて、心とからだを元気にする
- 血流をよくして中枢神経の機能を回復し安眠に導く
などの作用をもつ漢方薬で根本改善を目指します。
漢方薬は心とからだのバランスを整えるので、
寝起きの悪さや睡眠の質だけでなく、ほかの心身の不調にも
同時にアプローチできるのがメリットです。
漢方薬のなかには、
子どもが服用できるものもありますので、
選択肢のひとつとして考えてみてはいかがでしょうか。
朝の寝起き対策におすすめの漢方薬
・補中益気湯(ほちゅうえっきとう)
生命活動の根本のエネルギーである気が不足した
「気虚(ききょ)」の症状を改善する漢方薬です。
胃腸の働きを助け、消化・吸収を改善することで
元気を補う作用があります。
食欲がない、元気がない、疲れやすいなど
さまざまな症状に用いられます。
・苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)
水分代謝が悪く、体外に排出されるはずの余分な水分が
からだにたまっている「水滞(すいたい)」の症状を
改善する漢方薬です。
めまい、たちくらみ、動悸などの症状に用いられます。
しかし、寝起きに対する悩みはデリケートな面もあり、
どの部分を問題視するのかを決めるのは難しいですよね。
また、漢方薬は、自分の状態や体質に
うまく合っていないと、効果を感じられないだけでなく、
場合によっては副作用が生じることもあります。
そのため、「あんしん漢方」などの
オンライン漢方サービスに、
一度相談してみるのがおすすめです。
漢方に精通した薬剤師とAIが、
あなたに効く漢方薬を見極めて、
お手頃価格で自宅に郵送してくれます。
●あんしん漢方(オンラインAI漢方)
https://www.kamposupport.com/anshin1.0/lp/?tag=111432f3mmkr00010024
寝起きが悪い原因はひとつではないかも
朝が苦手になってしまう原因に、
思春期にみられる起立性調節障害が
隠れていることも多くあります。
自律神経失調症のひとつでもあり、
循環器系の調節がうまくいかなくなるため、
起きるのに時間がかかる病気です。
しかし、この疾患はストレスや環境的な要因も
関わって起こると考えられているため、
朝の寝起きが悪くても叱ったり、
無理に起こすことは避けましょう。
保育園や学校でのエピソードや、水分や塩分の摂取量、
食欲なども含めて総合的に考えることも大切です。
原因をひとつに決めるのではなく、
さまざまな面から子どもを観察し、
アプローチしてみましょう。
参考URL
National Sleep Foundation の推奨睡眠時間: 方法論と結果のまとめ
<この記事を書いた人>

あんしん漢方薬剤師
相田 彩(あいだ あや)
昭和薬科大学薬学科卒業。
総合リハビリテーション病院・精神科専門病院・調剤薬局の
現場で漢方薬が使用される症例を多く経験。
医薬品での治療だけではなく、
体質や症状に適した漢方薬を活用し
根本改善を目指すことの重要性を実感する。
現在は、症状・体質に合ったパーソナルな漢方を
スマホ一つで相談、症状緩和と根本改善を目指す
オンラインAI漢方「あんしん漢方」でサポートを行っている。
●あんしん漢方(オンラインAI漢方)
https://www.kamposupport.com/anshin1.0/lp/?tag=111432f3mmkr00010024