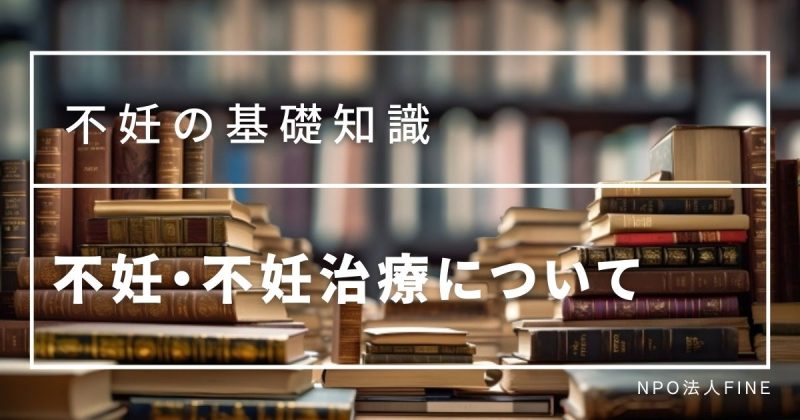2022年4月から、不妊治療の保険適用がスタートしました。
当初多くのメディアで取り上げられ、
高額な不妊治療の経済的負担の軽減が期待されていました。
保険適用から一年が過ぎて、
不妊治療の環境はどう変化したのか、
NPO法人Fine(以降Fine)のアンケート調査を
もとにご紹介します。
『NPO 法人 Fine「保険適用後の不妊治療に関するアンケート 2022」より』
不妊治療の保険適用の内容
不妊治療のうち、
- 一般不妊治療としてタイミング法、人工授精
- 生殖補助医療の体外受精、顕微授精(採卵・採精も含む)
- 生殖補助医療からの胚凍結保存、胚移植
が保険適用となり、
不妊治療の経済的負担が概ね軽減されました。
しかし、保険適用には、
- 年齢制限
(治療開始時において女性の年齢が43歳未満であること) - 回数制限
(初めての治療開始時点、女性の年齢が40歳未満の場合は通算6回まで)
(初めての治療開始時点、女性の年齢が40歳以上43歳未満の場合は通算3回まで)
の要件があります。
患者の状態に応じ
追加的に実施されるオプション治療のうち、
先進医療に位置付けられたものについては
保険診療と併用することができますし、
治療費が高額になった場合は
高額療養費制度を利用することが可能なケースもあります。
また、事実婚のカップルについても
保険制度は適用されます。
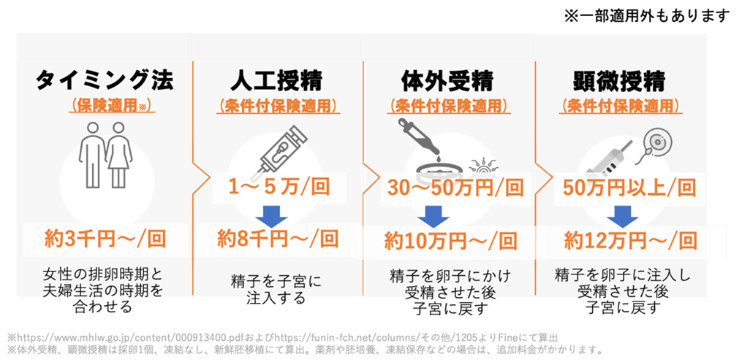
(図1)
詳しくは「厚生労働省_令和4年4月から、不妊治療が保険適用されています。」をご覧ください。
保険適用後、実際どうなった?
保険適用から一年経過して、Fineが実施した
「保険適用後の不妊治療に関するアンケート2022」の
結果からご紹介します。
保険診療を受けている人は47%。
保険診療+先進医療を受けている人は28%。
自由診療を受けている人は25%となりました。
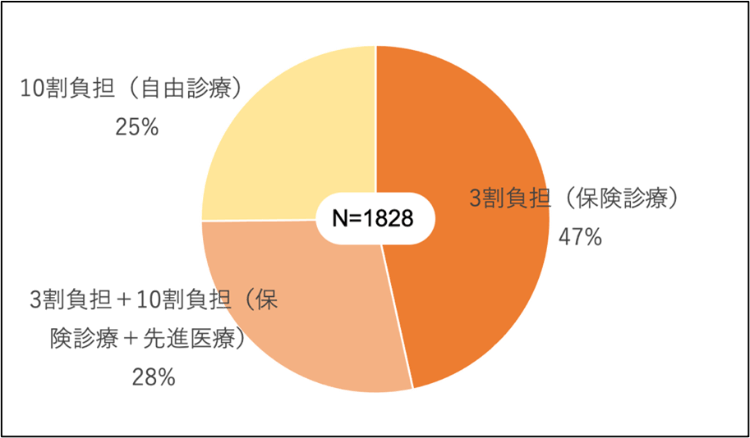
(グラフ1)
自己負担が3割(保険診療)のデータを年齢別に分けると、
20歳から35歳が約50%と、比較的若い年齢層である一方、
3割負担+10割負担(保険適用+先進医療)のデータを
年齢別に分けると、35歳以上が約70%でした。
支払う医療費が少なくなり経済的負担が軽減されたため、
以前よりも不妊治療をスタートしやすくなったようです。
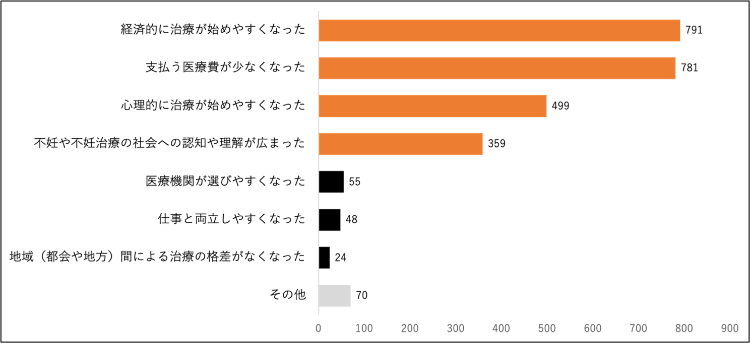 (横軸は人数)
(横軸は人数)
(グラフ2)
アンケートのコメント欄から、



など、経済的な負担の軽減が精神的な負担の軽減にも
つながっていることが伺えます。
医療機関が今まで以上に混雑していて、
待ち時間が増えたケースが多く見受けられました。
また保険制度の移行期間だったため
自分の使う薬が保険適用になるかどうかなど、
保険適用の薬などでわかりにくい部分があったようです。
さらに、経済的負担が多くなった
と回答した人も多くいました。
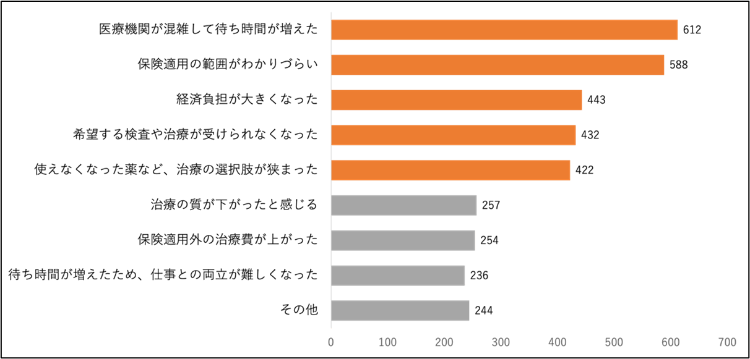
(グラフ3)
具体的には、




など、課題もあることがわかりました。
今後の課題について
不妊治療はオーダーメイド治療とも言われていて、
個人の体調や状態よって治療方針が異なります。
そのオーダーメイド治療を保険診療で
行なえるようにするために「標準化」が行なわれ、
治療の方法・進め方が統一されて
保険診療がスタートしました。
しかし、標準的な治療では
子を授かることができないケースもあります。
保険診療/先進医療/自由診療の中から、
自分に合うのはどの治療なのか、
医師とも十分に相談をして決定することが必要となります。
また、回数制限や年齢制限がある現在の制度は、
若い年齢であっても、この制限がプレッシャーとなって
精神的な苦痛を感じるという声も上がっています。
日本における国民皆保険制度が「国民全員」を
公的医療保険で保障するという考え方から見れば、
回数制限や年齢制限は緩和または撤廃してほしい
という声が大きいのも理解できます。
まとめ
不妊治療の保険適用に制限がある現状においては、
お子さんを授かりたいと思った時、
なかなか授からないなと思った時、
早めに医療機関の受診をお勧めします。
また、どの医療機関でどのような治療が受けられるのか、
ウェブサイトで参照するだけではなく、
医療機関で実施されている説明会などにも参加して、
カップルで話し合って
治療方針を決めていくことが必要となります。
妊孕性(妊娠するための力)は永遠ではありません。
限られた時間での治療となりますので、後悔しないためにも、
カップルでの早めの受診と
二人の意思の共有を行なうことが重要です。
もしお二人の考え方、意思の共有が難しい場合は、
カウンセリングをカップルで受けるという手段も有効です。
カウンセリングは
- 自治体が実施している通話相談
- 面接相談
- Fineが実施している不妊ピア・カウンセリング
などがあります。
相談員も産婦人科医や看護師、
自身も不妊を経験した不妊ピア・カウンセラー、
不妊ピア・サポーターなど、
今は多様な人材が相談員を担当しています。
ぜひ一度アクセスしてみてください。
【この記事を読んだ人におすすめ】
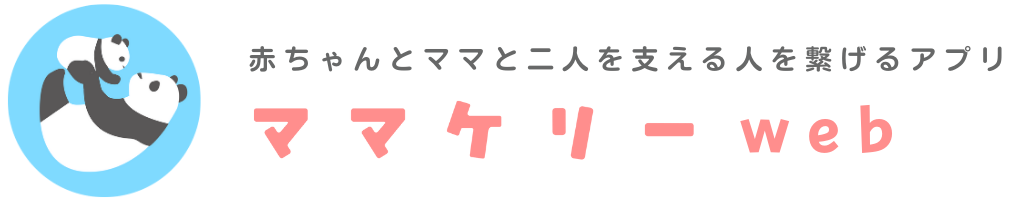

 2022年診療報酬改定で、不妊治療の保険適用拡大へ!変更ポイントを押さえましょう
2022年診療報酬改定で、不妊治療の保険適用拡大へ!変更ポイントを押さえましょう